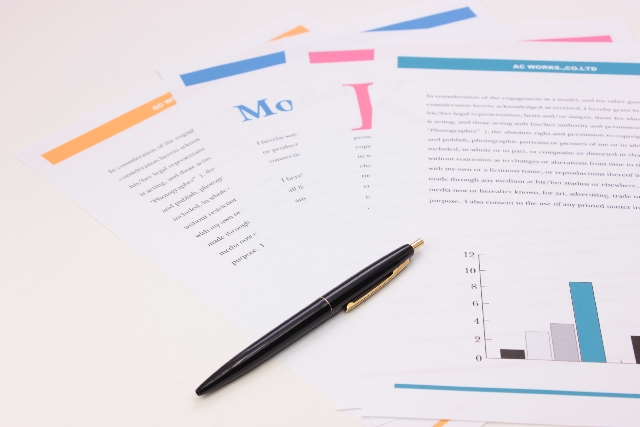


パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。
ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。
ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
失業のお手当は103万円に含めません。その代わりとして、「お手当をいただいている間は被扶養扱いにはなれない」ルールがあるわけです。
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
今の仕事を始める前、去年の9月頃まで失業保険を貰っていました。
それから次の仕事が見つかって、今派遣で働いているのですが、もうすぐ雇用保険を納め出しててから一年になります…。ずっと転職しようか悩んでいたのですが…
この場合、一年雇用保険を納めていたら、失業保険は貰えるのでしょうか?
今の仕事を始める前、去年の9月頃まで失業保険を貰っていました。
それから次の仕事が見つかって、今派遣で働いているのですが、もうすぐ雇用保険を納め出しててから一年になります…。ずっと転職しようか悩んでいたのですが…
この場合、一年雇用保険を納めていたら、失業保険は貰えるのでしょうか?
キッチリ12ヶ月以上雇用保険をかけていれば貰えます。
ただし、自己都合となりますので3ヶ月後からの支給となります。
ただし、自己都合となりますので3ヶ月後からの支給となります。
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
関連する情報